和歌山大空襲の記憶 細畠清一さんの体験朗読
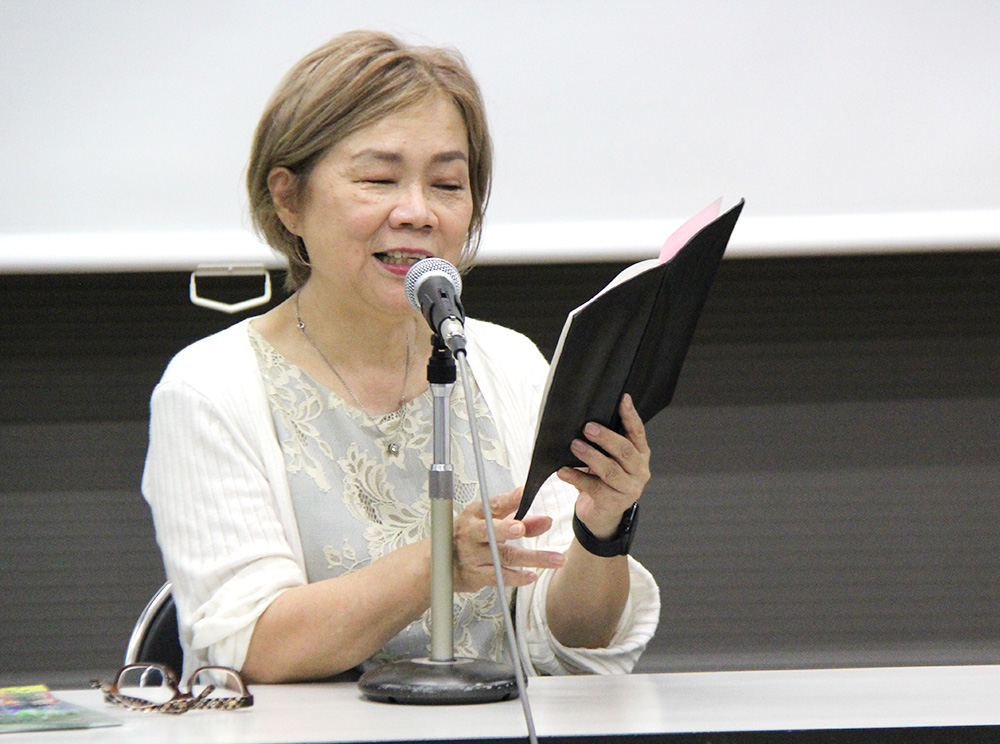
和歌山市内で5日、ある朗読が行われた。1945年7月9日深夜から10日未明の和歌山大空襲を伝える内容で、明日を生きる子どもたちへのメッセージもあった。「平和であることは、いいことだ。(中略)君たちは戦争を知らなくていい。それでいいんだ」――。空襲で姉を亡くした故・細畠清一さんの体験や思いを、生前、母校の小学校の児童に語った内容を含めて長女の美鶴さんが文章化。朗読家の福山ひでみさんがいのちを吹き込み、平和の尊さを伝えた。
細畠清一(静峰)さんは和歌山の書道教育・文化の発展に尽くし2022年に92歳で亡くなった。朗読は、細畠さんの回顧展の会場となった県書道資料館(西汀丁)で、昭和100年・戦後80年に合わせて企画。この日は細畠さんの95回目の誕生日でもあった。
当時、細畠さんは湊南尋常小学校の隣に住んでおり、15歳になったばかり。7月9日夜の警戒警報を受けて、母親と姉、兄との4人で庭の防空壕に避難。夜更けに本格的な空襲になり、三年坂から手平方面を目指して逃げたという。
朗読では、戦火から逃げようと和歌山城の堀に飛び込んだこと、二十歳の姉は火災旋風で巻き上げられ、城の堀の中から遺体で見つかったこと、岡口門のクスノキの下で死んだ姉を囲み、家族そろって三日三晩過ごしたことなどが語られた。県庁跡(現汀公園)に埋葬された遺体の多くは裸だったが、両親が防空壕に保管していた晴れ着を姉に着せて送ったことも朗読。福山さんは、場面や内容に合わせて抑揚をつけ、時に力強く、時に穏やかな語りで伝えた。
美鶴さんが父の体験を原稿にまとめ上げたのは、前日だった。思い出すのもつらい体験、身内を亡くした悲しみを抱え「子どもたちには一生、戦争を知らずに生きていってほしい」という平和への願い、日中戦争の発端となった盧溝橋事件のように、ささいなすれ違いやけんかが戦争の火種になりかねない恐ろしさなど、生前の父が語っていたことをメッセージに込めた。

美鶴さんは「父はあまり戦争の話をしなかったが、あることをきっかけに話すと、時間が動き出したようだった。つらい気持ちをはき出すことで、楽になったのではと感じることもあった。きょう父も朗読を聞いていたとすれば、とても喜ぶと思います」と福山さんに感謝を伝えた。
美鶴さんは毎年、7月9日に西汀丁で行われる追悼法要に出席。以前は少し怖い思いもあったというが、今では、吹き抜ける爽やかな風に、亡くなった人も今の平和を喜んでいるように感じ始めたという。
朗読の最後は、こう結ばれていた。
「忘れないこと、伝えていくことの大切さを時を追うごとに感じています。今後も、すっと心地よい平和の風を吹かせていくのが、生きている私たちの役目だと強く感じます」
この他、細畠さんの同級生で、同僚だった中村公一さん(94)が和歌山大空襲の体験を語った。
体験を語り継ごうと、生前の細畠さんや中村さんの証言を映像で残してきた和歌山大学観光学部の木川剛志教授が、聞き手となって進行。
中村さんはあの日、偶然にも岡口門で、細畠さんが亡くなった姉を家族と囲む姿を目にした記憶を紹介。市内の様子については「防空壕から逃げそうとした4、5人が、銅像みたいに逃げる格好のまま焼けていた」と惨状を伝えた。
「(たくさんの遺体が埋められた)汀公園は、あまり行きたくない場所。堀にも死体が浮いていて、今でも通るたびに、その有り様が浮かぶ」と静かに話した。



