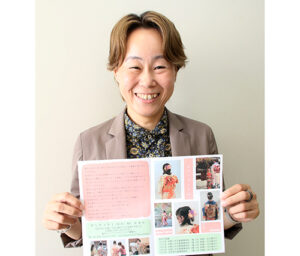「紀淡連絡道路」の構想

前号では、山上と市街地に構成され珍しい遺構が残る「洲本城」を取り上げた。洲本城跡に建つ模擬天守の周囲は市街地と紀淡海峡を望む展望台として整備されている。南東の方角に目を向けると友ヶ島、その先には和歌山市が見える。
直線距離では10㌔程度の隣町でありながら、陸路による道のりは大阪ルートで160㌔程度と遠い。かつてから、和歌山・大阪南部と淡路島・四国のアクセス向上を目指した道路の建設が検討されている。実現性に課題はあるが、地域を結ぶ架け橋として期待される「紀淡連絡道路」の構想を紹介したい。
紀淡連絡道路は、約11㌔の紀淡海峡を横断し、和歌山市と洲本市を結ぶ全長約40㌔の幹線道路。海峡部には明石海峡大橋を上回る世界最大級のつり橋となる「紀淡海峡大橋」が架けられるという壮大な計画である。
1965年に構想が始まり、87年に大阪湾環状交通体系に位置づけられ、91年度には当時の建設省による調査が開始された。92年、実現に向け周辺市町村が「紀淡海峡連絡ルート実現期成同盟会」を設立。和歌山県・兵庫県・大阪府の23市町村で構成され、早期実現に向けた要望活動や、調査研究、広報活動を行っている。
2023年に閣議決定された国土形成計画では長期的視点から取り組むとされている。実現の時期は未定だが両市を結ぶ夢のある構想。地域に求められ、開通による効果が訴求でき、さらに環境に配慮したものとなれば夢が現実になるかもしれない。そのためにもまずはこの地域で暮らす私たちが、それぞれの魅力を理解し交流を深めることが大切だろう。(次田尚弘/洲本市)