「副業人材」を活用 道の駅すさみの取り組み

和歌山県南部に位置するすさみ町。2015年、この地に地域の玄関口として誕生したのが「道の駅すさみ」である。運営を担うのは、和歌山を中心に飲食店やホテル、温泉事業を積極的に展開する株式会社信濃路だ。開業以来、「地域ファースト」を経営理念に掲げ、観光客と地元住民の双方に愛される施設づくりを進めてきた。
道の駅すさみが挑んだ新しい経営戦略と広がる可能性
「信濃路」はこれまですさみ町で、地元漁業者と連携した鮮魚店の立ち上げや、地域生産者と協力したマルシェの開催、また、道の駅に隣接する宿泊施設「TUZUMI WAKAYAMA SUSAMI」も手掛けるなど、多様な取り組みを展開してきた。単なる休憩施設ではなく、地域に根差した複合施設として道の駅を育ててきたのである。
しかし、その順調な歩みの裏には、将来に向けた大きな不安が立ちはだかっていた。2027年に予定される紀勢自動車道の延伸により、すさみ町を経由する観光客が減少する可能性が指摘されていたのだ。これまで道路利用者の「立ち寄り需要」に大きく支えられてきただけに、来客数の大幅減は避けられないと見られていた。
さらに町全体に目を向けると、人口の流出、高齢化とこれに伴う地域経済の縮小といった課題が進行しており、従来型の運営では未来を描くことが難しい状況にあった。地域に根差す企業として、いかに「道の駅すさみ」を進化させるのか――。その答えを模索する中で、副業人材の活用という新しい選択肢に出会うことになる。

「副業」への認識が変わった瞬間
「副業人材」という言葉を耳にしたとき、信濃路の冷水康浩社長は、正直なところあまりピンとこなかったという。心に浮かんだのは「どこかで仕事を探していて、時間が余っている人を一時的に雇ってあげるような存在」というイメージに過ぎなかった。自社の課題解決に直結するようなプロフェッショナルな人材を、外部から副業という形で迎え入れるという発想は、当初まったく持ち合わせていなかったのだ。
しかし、その認識は、「和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点」から副業・兼業プロ人材活用の仕組みについて紹介を受けて、大きく変わった。企業が抱える経営課題に対し、外部の専門的な知見を持つ人材が、自身の豊富な経験を活かして伴走する――。説明を受けて、それまでのイメージが一気に覆される思いだった。
「自分たちにはない新しい視点や考え方を提供してくれる。そして顧客に響く発信方法を教えてくれる。まさしくプロフェッショナルを“借りる”という感覚でした」と冷水社長は振り返る。
同社はこの新しい概念に大きな可能性を見いだした。それは単なる人手不足の解消策ではなく、企業が成長していくための「戦略的な武器」となり得るものだった。この気づきこそが、道の駅の未来をかけたプロジェクトの幕開けとなったのである。
想像超える反響と多様な人材
副業人材の活用を検討した信濃路が実際に募集を開始すると、その反響は予想を大きく上回るものだった。案件を公開した途端、次々と応募が寄せられ、短期間で23名もの人材からエントリーがあった。応募数が想定を大きく超えたため、同社は途中で選考を締め切らざるを得なかったという。
しかも集まった人材の顔ぶれは実に多彩だった。行政と連携しながら道の駅の企画に携わった経験を持つ人、地域活性化のプロジェクトを多数手掛けてきた人、さらには音楽や映像といった異業種の分野から新しい提案を掲げる人まで幅広かった。応募者の多くは「自分の経験を地域活性に役立てたい」と強い思いを持ち、真剣な姿勢で応募してきた。担当者はその熱意に触れ、「自分たちがこれまで培ってきた経験を、地方創生や地域活性のために役立てたいという人がこんなにも多いのか」と驚きとともに大きな期待を抱いたという。
面談を重ねる中で、信濃路の担当者自身も多くの学びを得た。他地域の道の駅の事例を知ることで、自社が直面する課題を相対的に捉え直すことができた。また、自分たちだけでは思いつかなかった新しい提案に触れることで、発想の幅が大きく広がったという。この面談プロセスそのものが、貴重な情報収集の機会となった。
最終的に採用を決めたのは、過去に道の駅をプロデュースした実績を持ち、さらに「自ら現場に足を運び、地域の人々とともにプロジェクトを推進したい」という強い熱意を示した東京在住の人材だった。同社はその副業人材とともに、道の駅すさみの未来を見据えた挑戦に踏み出したのである。

現地視察から始まった伴走支援
採用された副業人材は、まず最初に現地を訪れることを希望した。施設の現状や運営の実態、そして働く人々の姿を直接見て、地域の空気を肌で感じたいという強い思いがあったからだ。
「最初から最後までリモートでは、絶対に伝わりきらない部分があります。初めに現地まで来てくださったことで、その後のコミュニケーションは格段にスムーズになりました。道の駅の空気感や地域の人々の暮らしを共有できたことで、議論の深さが全く違いました」――冷水社長はこう振り返る。
現地視察を終えた副業人材は、東京に戻ってから早速提案書の素案を作成。その後はオンライン会議を繰り返しながら、信濃路が掲げるビジョンと副業人材の提案をすり合わせていった。互いに意見を出し合い、何度もキャッチボールを続けることで、両者の思いは次第に一つの形へと凝縮されていった。
このプロジェクトにおける大きな成果のひとつが、「可視化」である。完成した提案書は、同社が描く道の駅の将来像を明確に言語化し、誰もが理解できる形に可視化したものとなった。それは社内にとっての羅針盤となっただけでなく、施設の所有者である「すさみ町」と共通認識を築くうえでも極めて重要な役割を果たした。
ちょうどその頃、道の駅の指定管理更新に向けた企画提案の時期が重なっていた。副業人材と共に練り上げた経営戦略は行政への提案書に盛り込まれ、その成果として引き続き指定管理者として採択されることになった。提案書は単なる資料にとどまらず、次のステージに進むための揺るぎない土台を築き上げたのである。


「通過点」から「滞在拠点」へ 新たな道の駅像を描く提案
完成した提案書に盛り込まれたのは、単なる施設改善にとどまらない、地域とともに歩む新しい道の駅のコンセプトだった。従来のバーベキューエリアは、正直なところ観光客の心を大きく引きつけるほどの魅力はなかった。しかし副業人材は、地元漁業者から直接仕入れた新鮮な海産物を用い、観光客が地元の食文化を体験できる「見せ方」を提案したのである。
さらに、レストランメニューの刷新や土産物コーナーにおける地元商品の拡充など、観光客が「道の駅すさみに行きたい」と目的地として選ぶ理由を一つひとつ積み重ねていく戦略も示された。
これらの施策は、自動車道の延伸によって道の駅が単なる「通過点」になってしまうという危機感への、明確な答えだった。「目的地」としての価値を創出することで、道の駅を単なる休憩施設から、地域を牽引する滞在拠点へと進化させる――。こうした発想は、副業人材の視点があったからこそ実現できたものだった。
副業人材との協働は、初回の現地訪問を除けば、基本的にリモートで進められた。最初の段階では2週間に1度の打ち合わせで進捗を確認し、計画が固まってきた段階では月1回のペースに移行。メールでのやり取りを重ねながら、進行状況を随時共有した。
オンラインを中心としながらも、最初に現地を訪れたことが信頼関係の構築に大きく寄与した。そのおかげで以後のコミュニケーションは格段に円滑となり、議論や意思決定のスピードも向上したという。
現在は、策定された計画をもとに、社員が現場で具体的な実行を進めている。副業人材との取り組みは一区切りを迎えたものの、今後も必要に応じてスポット的に相談したり、クリエイティブ面での協力を依頼したりする可能性は残されている。
このプロジェクトを通じ、副業人材との協働が、単なるアドバイスにとどまらず、計画の具体化と実現を加速させる重要な手段であることが確認された。外部の専門知見を柔軟に取り入れることで、社内の人的リソースを最大限に活かしながら、地域に根差した施設運営を進めることが可能になったのである。
社員のマインドチェンジという最大の収穫
今回の取り組みで得られた成果は、提案書の完成という直接的なものにとどまらなかった。もうひとつ、いや場合によっては最大の成果は、社員の意識に生まれた変化である。
策定した事業計画を社内で共有したことで、現場スタッフのモチベーションは大きく向上した。外部のプロフェッショナルからもたらされた新しい視点は、社員自身の仕事への向き合い方を変えるきっかけとなった。ミーティングや会議での報告は刺激となり、他部署の社員も「自分たちも新しい挑戦をしてみよう」と意欲を抱くようになったという。
「道の駅すさみ」の挑戦は、地方に根差す企業が副業人材を活用することで、事業の可能性を大きく広げられることを示している。専門人材の知恵を借りながら地域とともに歩む姿勢は、人口減少や産業構造の変化に直面する多くの地域にとっても参考になるはずだ。
信濃路が描いた新しい経営戦略は、すさみ町の未来を支えるだけでなく、副業人材活用という仕組みが全国の企業に広がる契機となる可能性を秘めている。課題を抱える企業にとって、副業人材は単なる「外部の助っ人」以上の存在である。共に地域の未来を切り拓き、事業の成長を後押しする、揺るぎないパートナーなのだ。
この取り組みを通じて得られた知見や経験は、地域企業にとっても新たな可能性を示す灯台となる。副業人材の活用は、企業が抱える課題を解決するだけでなく、社員の意識改革や組織の成長、地域との連携強化にもつながる。地方企業が持続的に発展していくうえで、欠かせない選択肢のひとつとして注目されるだろう。
地域企業へのメッセージ
今回の取り組みを通じて、信濃路は副業人材の可能性を強く実感している。
「副業という仕組みを通じて、自分の知識や経験を地域に役立てたい、社会に貢献したいと考える人がこんなにも多くいることを知りました。そして、そうした熱意あるプロフェッショナル人材と企業が、必要な部分を、必要なときだけ業務を共にするという関係性が、これほどまでにうまく機能するとは思っていませんでした。それも、極めて安価なコストで活用できます」――冷水社長はそう語る。
同社は、この経験が地域の企業にも広まってほしいと考えている。「まずは気軽に試してみてほしい」と呼びかける。副業人材の活用は、単なる労働力不足を補う手段にとどまらない。企業に新しい視点をもたらし、社員の意識を変え、停滞した状況を打破するきっかけとなる。地域に根差す企業が未来を描くための大きなヒントが、そこにある。
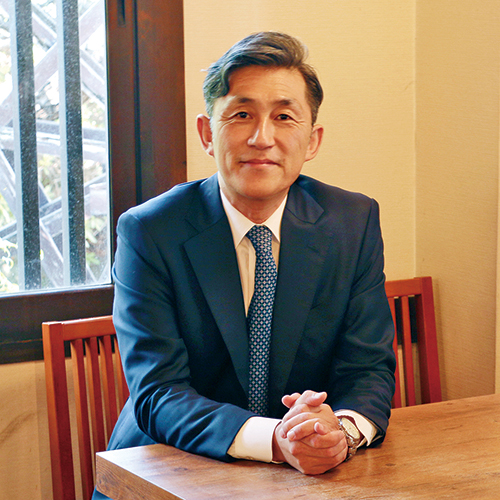
お問い合わせ先
公益財団法人わかやま産業振興財団・和歌山県プロフェッショナル人材戦略拠点(フォルテワジマ6F)、℡073・433・3110、メールpro-jinzai@yarukiouendan.jp


