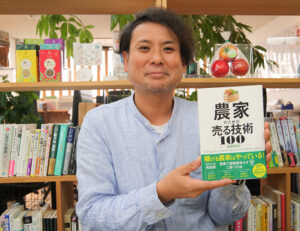鮮度が命、「鰆」の魅力

前号より、産卵期である春にかけ瀬戸内海で取れ、春の季語としても知られる「鰆(さわら)」を取り上げている。鮮度が落ちやすい鰆であるが、洲本では漁場の近さを生かし刺し身などの生食として食べることができ、それがブランド化されている。今週は地域で人気を博している鰆の料理について紹介したい。
洲本における鰆の生食文化は、2006年に洲本市と合併した旧五色町の漁師めしとして親しまれてきたもの。ハレの日とされる地域の祝い事の場で、刺し身やタタキとして振る舞うことが慣わしとなってきた。
地域の文化と地場産品の魅力を伝えるため、新たな名物を作ろうと協議会が立ち上がり「生サワラ丼」が考案され、2014年から複数の飲食店で販売を開始。旧五色町は淡路島の西海岸(播磨灘)に位置する地域であるが、東海岸(紀淡海峡)側の市街地の地域にも拡大し、現在は約20の店舗でお店ごとの趣向を凝らしたオリジナルのメニューが提供されている。
鰆をすしで食べてみた。柔らかい身と、とろける食感が特長で、さっぱりとした味の中に甘さを感じる。新鮮であるほど身が柔らかくまるで中トロのようと評され、漁場で取れてから飲食店で提供されるまでのスピードが勝負。ご当地を訪れなければ食べることができない逸品である。
地域で親しまれる鰆であるが、近年は漁獲量の減少が顕著。地球環境の変化などが要因で、1987年に兵庫県内で2000㌧以上あったものが、98年には数十㌧にまで減少。サイズが小さい鰆の漁獲を避け、漁ができる期間に制限を設けるなど、鰆の個体維持と文化の伝承の両輪で、地域が一体となった取り組みが進められている。
洲本における漁期は11月末まで。脂がのった鰆の漁師めしをぜひ。(次田尚弘/洲本市)