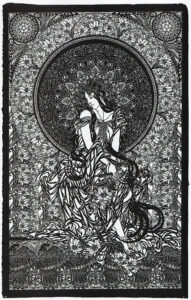難治性の傷の治療に光 県立医大が仕組み発見

糖尿病患者の傷が治りにくくなる原因と低下した自然治癒力を改善する仕組みを、和歌山県立医科大学医学部法医学講座の石田裕子准教授、國中由美特別研究員らの研究グループが発見した。足の切断にもつながりかねない糖尿病性皮膚潰瘍や、寝たきり状態の高齢者などに見られる床ずれの褥瘡(じょくそう)など、難治性の傷を治す新しい治療法につながることが期待される。
糖尿病になると、けがをしても皮膚の傷がなかなか治らない場合があり、特に足などの傷は感染や壊疽(えそ)を起こし、最悪の場合は足の切断に至る。糖尿病患者は日本に約1000万人、世界に約6億人といわれ、難治性の傷の治療による経済的負担、生活の質の低下は、世界的で深刻な社会問題といえる。
健康な人の傷が治る過程では、傷をふさぐ細胞である「線維芽細胞」が働き、血管の形成や皮膚の再生が促されるが、糖尿病患者は、血流の低下や炎症の異常により線維芽細胞がうまく働かず、傷の治りが遅くなる。
そこで今回の研究は、線維芽細胞に働きかけて修復に必要なコラーゲンなどを作らせる信号を出すたんぱく質「オンコスタチンM(OSM)」と、その受け皿「OSM受容体β(OSMRβ)」に注目した。
正常なマウス、糖尿病マウス、遺伝子操作によってOSMRβを欠損させたマウスで傷の治り方を比較し、OSMRβ欠損マウスは治りが遅く、線維芽細胞も血管形成も少ないことを確認。さらに、糖尿病マウスの傷にOSMを投与することで、血管形成などが増え、遅くなっていた治癒が改善することが分かった。
糖尿病性皮膚潰瘍の治療はこれまで、感染を防ぐ処置や血糖のコントロールが中心だったが、今回の研究で明らかになったOSMとOSMRβの仕組みを活用することで、「傷が治る力」を根本的に回復させる薬の開発などが期待され、床ずれや手術後の傷の回復促進、高齢者の皮膚修復機能の維持などに応用できる可能性も広がる。
県立医大で研究成果の発表が行われ、近藤稔和教授、石田准教授、國中特別研究員が出席。石田准教授は「OSMは元々体内にあるものなので、薬は副作用を最小限に抑えられると考えられる」と説明し、「治りにくい傷に苦しむ人を救いたいというのが研究の原点。一人でも多くの患者を支え、安心して日常生活を送れるように挑戦を続ける」と話した。
今回の研究成果は10月28日、国際学術誌「Communications Biology」にオンライン掲載された。